『デジタル未来にどう変わるか?』インタビュー(1)
全2190文字
AI関連のニュースは以前より少なくなったように思いますが、それはAIが普通のことになってきたからだとも言えます。テクノロジー基点のイノベーション創出を専門とされている岸さんは、今のAIをどのように見ていますか?
岸浩稔氏 ディープラーニングと半導体技術など、ソフトウエアとハードウエアの進化のタイミングがピタリと合って、今のAIは「限られたタスク」であれば実務として使える能力があります。だから注目を浴びているのですが、私は、「AIは蜃気楼(しんきろう)のようなもの」という、ある先生から聞いた言葉の通りだと思っています。「追いかけても追いかけても少し先に見えてつかめないもの」という意味です。
ちょっと昔の話をすると、ゲームの「ドラゴンクエスト」で使う作戦コマンドはAIと呼ばれていましたし、パソコンOSのWindowsに現れたイルカもAIだと言われました。いつの時代であっても、常に私たちの少し先にある何かすごそうなテクノロジーをAIと呼んでいるのです。これからも、そうなんだろうと思います。
AIが蜃気楼なら、AIによる変革も蜃気楼のようなものでしょうか?
岸氏 AIはテクノロジーの象徴のような言葉です。AIは蜃気楼のようなものでも、テクノロジーが社会を変えてきたのは紛れもない事実です。これからもそれは変わらないし、むしろ、そのスピードはますます速くなっていくと思います。大事なことは、AIというつかみようがない使われ方をしている言葉や、目先のはやり言葉に惑わされることなく、社会が技術によってどう変わろうとしているのかに注目することだと思います。
英オックスフォード大学の論文の一部を切り取って、「AIが人の仕事を奪う」というメッセージが世界を駆け巡りました。先端技術を使った新規事業を数多く手掛けられている光谷さんは、このメッセージをどのように捉えていますか?
光谷好貴氏 これからもAIが人の仕事の領域に入ってくるでしょう。効率性の観点でいえば、AIをどんどん活用したほうがいいと思います。人がやるときつい仕事であっても、AIは何の文句も言わずに働いてくれますからね。これをもって「AIが仕事を奪う」というなら、「どうぞ奪ってください」という人は実はたくさんいるのではないでしょうか。
社会人なら誰でも経験したことがあると思いますが、ひたすら単純労働を繰り返すような仕事を割り振られ、つらいけど、これを終わらせないと次に進めないのでやらないわけにはいかない。そういう仕事はたくさんあります。そんな雑用こそが大事という意見もありますが、創造的な仕事がしたいと思っている人にとっては苦痛でしかないと思います。そういう単純労働をAIがやってくれて、人は創造的な仕事に専念できるなら、こんないいことはないですよね。
もちろん、すべての人が創造的な仕事をしたいわけではないと思いますが、AIが人の仕事をしてくれるようになって、「自分のしたい仕事が何かを考えられる時代になった」と言えると思います。AIによる仕事への影響には、プラス面のほうが大きいように思います。
マイナス面よりプラス面に注目しようよ、ということですね
光谷氏 ただ、プラスだからといって「楽になる」わけではないと思います。散々言われてきたことですが、パソコンが登場して不要になった仕事はたくさんありますが、パソコンが登場してからのほうが人の仕事は忙しくなっています。AIはパソコンよりもっと人の代替可能性が高いので、AIの登場で人がやらなくてもよくなる仕事は増えると思いますが、それを上回る新しい仕事が生まれ、「仕事が楽になる」とはならないと思います。
今までになかった仕事が生まれるからこそ、「自分がしたい仕事」を考え、それができるスキルを身に付けていく、そういうことが大事じゃないでしょうか。(次回に続く)
デジタル未来にどう変わるか?
AIと共存する個人と組織
デジタル未来にどう変わるか? AIと共存する個人と組織
著者●上田恵陶奈、岸浩稔、光谷好貴、小野寺萌/定価●2750円(税込み)/発行●日経BP/判型●A5判232ページ/発行日●2021年9月13日/ISBN 978-4-296-10991-3
英オックスフォード大学の研究に端を発する「AIが仕事を奪う」 というメッセージに世界は驚き、一時は「AI脅威論」が語られました。しかしそれは程なく「人とAIの共存の始まり」と理解されるようになりました。
私たちの未来はAIと共にあります。それは、どんな世界、どんな働き方になるのでしょうか? 本書は、その問いに向き合った研究成果です。4人の研究者による足かけ5年に及ぶ活動の成果が本書にまとめられています。
本書を読めばデジタル時代に身に付けるべき能力が分かり、成功の具体的なイメージが描けるようになるでしょう。研究者の高い志のおかげで、読み終わって悲観的になることはありません。デジタル社会を生きるすべての人々に読んでもらいたい1冊です。
からの記事と詳細 ( AIと共存した働き方とは何か? デジタル未来の研究者に聞く - ITpro )
https://ift.tt/3jTtUFM

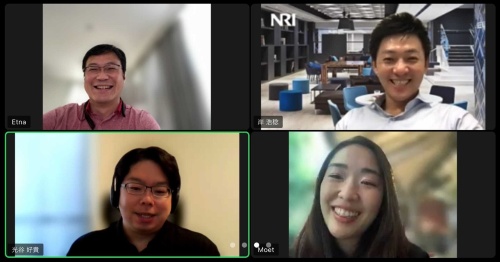

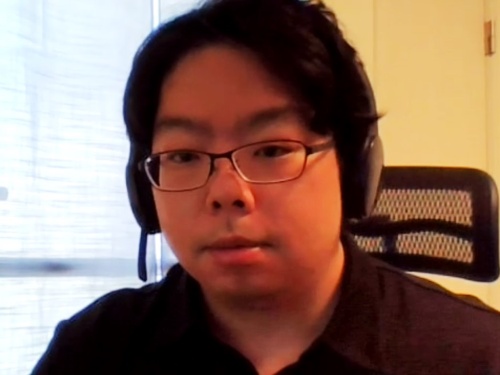


No comments:
Post a Comment